奥州南部糠部三十三カ所観音巡礼 /Oshu-Nanbu-Nukanobu 33 Kannon Pilgrimage
青森県、岩手県にまたがる、旧・糠部郡33カ所の観音霊場。


青森県、岩手県にまたがる、旧・糠部郡33カ所の観音霊場。
糠部郡とは、現在の青森県東部から岩手県北部にかけての旧地名です。
平泉藤原氏討伐で功績を挙げた南部三郎光行(永万元年(1165年)~嘉禎2年(1236年))が、文治5年(1189年)に源頼朝から糠部五郡の地を賜って地頭職となり、現在の三戸郡南部町に平良ヶ崎城/平良ヶ崎館を築いたと伝えられています。この糠部五郡の範囲については諸説あるものの、現在の二戸、三戸、八戸、九戸の地域ではないかと言われています。
南部光行は奥州における南部家一族の元祖と言われます。
糠部郡は「九ヵ部四門の制」によって、一から九までの「戸」に分けられ、余った四方の辺地を東西南北の「門」と呼んだと言われています。
この地域は「糠部の駿馬」と言われた名馬の産地で、「戸」は「牧場」の意味であるとも言われています。
現在もその地名は、岩手県一戸町、二戸市、青森県三戸町、五戸町、六戸町、七戸町、八戸市、岩手県九戸村として残っています。四戸という地名は残っていませんが、「四」は「死」を連想させることから、「朝を見ず=死」の意味として、現在の五戸町浅水が四戸であったという説もあります。
朝廷と蝦夷との38年にも及ぶ戦いが終結した弘仁2年(811年)から弘仁4年(813年)にかけて行われた蝦夷征伐において、この地域は一気に平定されました。その後に置かれた拠点に「柵の戸」を設け、軍事行動の拠点として整備した際、それぞれを「一のきのへ」「二のきのへ」というように呼んだものが、煩わしさから「きの」を省いたのが、それぞれの地名の語源とも言われています。
特に一戸から七戸までは北に向かって約20キロメートル間隔となっていて、これは1日の行程に相当します。この説に従えば、行軍の軌跡を示しているのかも知れません。
また、「門」のうち北門は、現在の青森県上北郡、下北郡としてその名残があります。
観音菩薩は、あまねく衆生を救うために、相手に応じて仏身、声聞身、梵王身など、33の姿に化身するとされます。
そのため、観音信仰において「33」という数字は重要な意味を持ち、三十三間堂(蓮華王院本堂)、西国三十三カ所観音霊場などはそこに由来しています。
西国三十三カ所観音霊場は、現在の和歌山県、大阪府、奈良県、京都府、滋賀県、兵庫県、岐阜県に点在する33カ所の観音菩薩を祀る霊場です。
養老2年(718年)に現在の奈良県桜井市にある長谷寺の開基である徳道上人が、閻魔大王から託された宝印に従って定めたとされています。
また、同様の三十三カ所観音霊場は日本各地に存在します。
奥州南部糠部三十三カ所観音霊場は、寛保3年(1743年)に八戸天聖寺八世・則誉守西上人によって定められた観音信仰の霊場で、現在の青森県八戸市、三戸郡階上町、南部町、三戸町、田子町、岩手県二戸市、二戸郡一戸町、九戸郡軽米町に点在しています。
場所がわかりにくいところもありますが、何かの機会に巡礼してみてはいかがでしょうか。
駐車場や駐車スペースの無いところ、個人宅や医院の敷地内となっているところもありますので、参拝の際はご迷惑にならないよう、ご注意下さい。
奥州南部糠部三十三カ所観音霊場が紹介されている本です
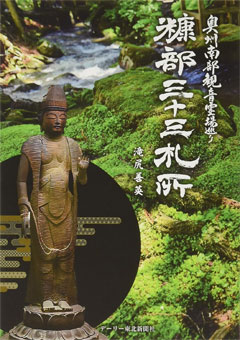
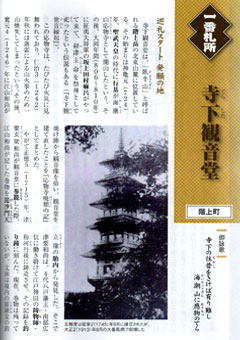
滝尻善英 著/デーリー東北新聞社
奥州糠部三十三観音霊場を紹介しています。
参拝方法や作法、身支度についても紹介され、別冊の携帯用巡礼案内も付属するなど、糠部三十三観音霊場を巡るための必携本となっています。